絹(シルク)の歴史

シルク(絹)は、蛾の幼虫「蚕(カイコ)」の吐き出す繭から作られる天然繊維です。
蚕を育てて繭(まゆ)をとることを養蚕(ようさん)といいます。
養蚕は紀元前6000年ごろ中国の黄河や揚子江流域で野生のクワコを家畜化したことが始まりといわれます。
紀元前1000年ごろから一般の農家でも養蚕を行うようになりましたが採れた絹は、宮廷にすべて献上されていました。

紀元前200年ごろ、漢の時代になると西域との貿易が始まり、異民族を支配するための褒美として絹が使われるようになったといわれています。
その時代、絹織物は同じ重さの「金」に交換される程、大変貴重な物として扱われていたといわれています。
こうして貴金属と交換された絹織物は中近東、ヨーロッパ・北アフリカを結ぶ東西交易路を通じて伝わっていったとされています。
やがて、この交易ルートが「シルクロード」(絹の道)と言われ、東西文化の交流に多くの役割を果たしました。

中近東では細やかな織り、鮮やかな染色、エキゾチックな文様が特長のシルク織物が発展しました。
「ペルシャ絨毯」はシルク織物として代表的な製品の一つです。

日本にシルク(絹)がいつ伝わったのかは未だにはっきりとは分かっていません。
しかし、シルクロードが出来るより遥か前の弥生時代の遺跡から絹織物が出土されています。
このことから日本には弥生時代ごろにはすでに伝来していたと考えられ日本でも他の国と同様に高級品として扱われていました。
佐賀県の吉野ケ里遺跡からは、中国へ贈っていたと推察される様々な絹織物が出土されていますが中国の絹織物とは糸使いなどが異なっていたこと、そして日本書紀、古事記にも養蚕に関する記述があることからも日本独自の養蚕と絹織り・染色の技術が発展したと考えられています。
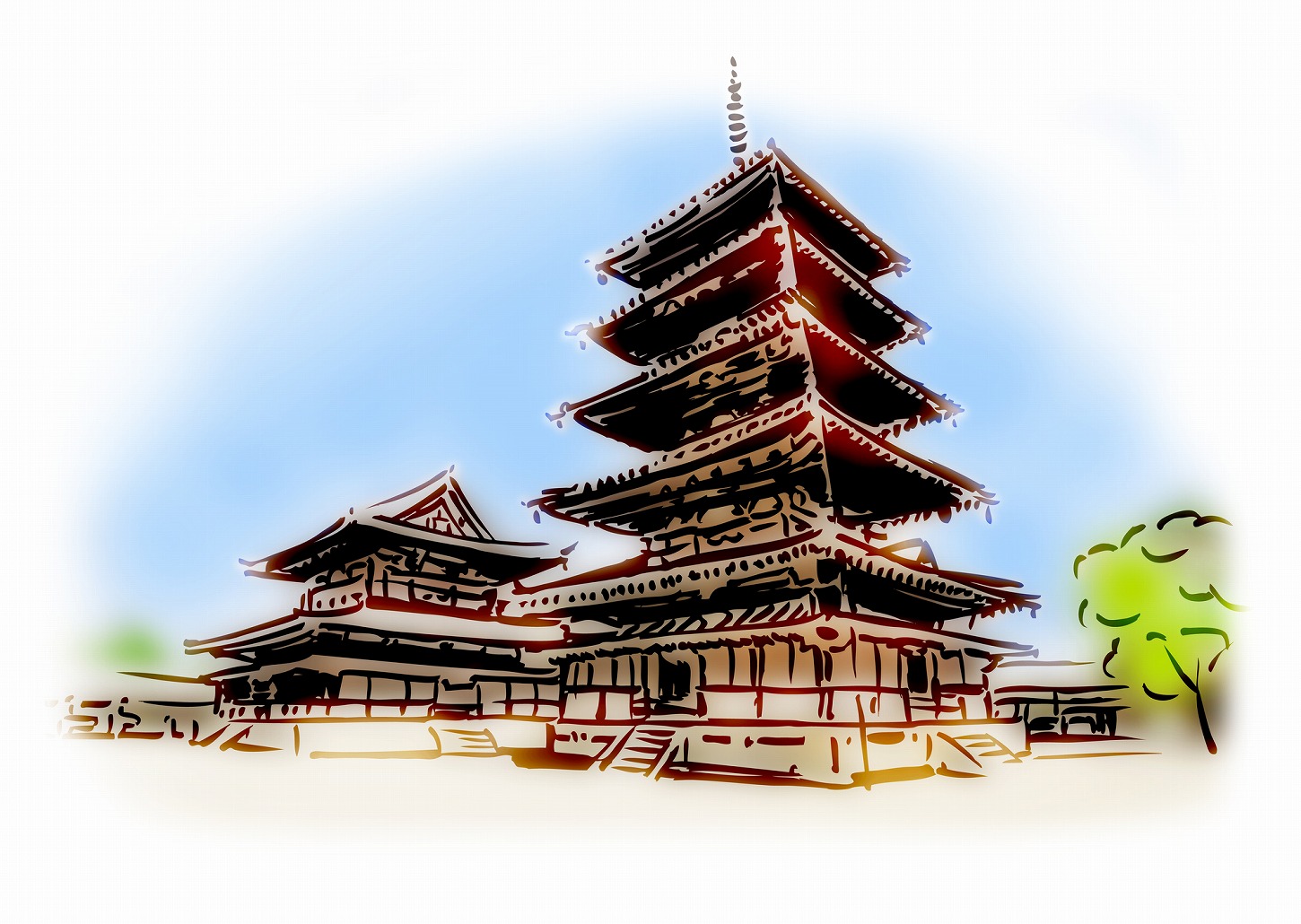
飛鳥時代の頃には中国・朝鮮半島からの渡来人が増え始め、養蚕・製糸・染色の先進的な技術が伝わったと考えられています。
この時代の税制である租庸調の「調」は繊維類を納めるものとされ、絹(シルク)を納税として納めていたとという文献も残っています。
養蚕は九州から技術が伝わり、そして西日本一帯へと広まっていき各地で独自の発展をしていったと考えられています。
中国のシルクロードを「西のシルクロード」と呼ぶのに対し、中国・朝鮮半島から日本に持ち込まれたルートは、「東のシルクロード」と呼ばれています。

奈良時代になると養蚕は、北海道・東北を除き、日本全国で行われるようになりました。
この頃から、絹製品は貴族たちの服や素材として扱われていきました。

平安時代に入り、現在の着物のような日本伝統の和装が生まれ、独自の文様の絹織物が作られるようになりました。
しかし、鎌倉時代になると「質素」が美徳であると考えられ、絹織物の一大産地であった京都の織物は衰退していったそうです。
その代わりに地方の絹産業が活発化し、京都の絹織物技術が伝わっていくきっかけになりました。

そして室町時代から安土桃山時代頃には錦、緞子、朱珍、絣、紬などの多彩な糸を用いた先染めによる高級絹織物「西陣織」が誕生しました。
現在も愛されている「丹後ちりめん」や「京ちりめん」が作られるようになったのもこの頃からだといわれています。

この時代に作られた絹製品はその美しさと質の良さで高級品の範疇を超えていたようです。
しかしそれもつかの間、戦乱の絶えない激動の時代に入り、日本の絹の品質はどんどん下がり高級品とは名ばかりの劣悪なものになっていきました。

戦乱の世が終わり、粗悪品に成り下がってしまった日本の絹は品種改良が進められます。
長年の研究と努力の結果、江戸時代中期には日本の絹製品は、世界でも有数の絹産地、中国産の絹製品に引けをとらない上質なものへとなりました。

高級品としてふたたびその地位を取り戻した絹製品ですが日本国内の絹だけではその需要を賄うことが出来なくなり中国から生糸を輸入するようになりました。
生糸の「代金」として日本は国産の銅を充てていましたが、絹織物の需要拡大で中国から生糸を買いすぎてしまい、国内の銅が半分以上なくなる事態となりました。
この事態に時の幕府は、「中国から生糸を輸入しなくて済むように」と養蚕を奨励する「お触れ」を出すとともに、贅沢禁止令を発令し絹織物の多くは贅沢品として庶民は禁じられることとなったというエピソードもあります。
しかし、そんな中でも紬だけは庶民も着用することが許され、落ち着いた色合いが江戸の粋(いき)と愛されていました。

上級な武士や一部の貴族だけが着用を許された高級な絹製品。
下級の武士や庶民が手にれることは容易ではない絹製品を、一般庶民でも扱えるようにしたいと考えた絹織物産業は猛烈なスピードで技術発展が進みました。
西陣織の産地の高い技術を学んだ各地の職人たちが生み出した絹織物は、その土地ごとに独自の進化を遂げていきました。
その中でも「金沢の友禅染」「茨城の結城織」「山形の米沢織」などは特に重宝され現代も愛され続ける上質な絹織物となりました。

江戸時代後期から末期になると製糸の機械化が始まり、明治時代になると日本の養蚕業製糸業は最盛期を迎えます。
ちょうどそのころ世界の絹産地で蚕の病気「微粒子病」のパンデミックが起こり世界の養蚕業は壊滅的なダメージを受けたことから世界中で日本産の絹の需要が急増、輸出量が爆発的に拡大します。
需要拡大に伴い明治政府も養蚕・製糸業を推進したことから関東・中部地方を中心に近代的な製糸工場が次々と創業を開始しました。
日本の製糸産業で一時代を築いた「富岡製糸場」が生まれたのもこのころです。
1900年頃日本は世界最大の絹輸出国となりました。当時、国内の農家の約4割が養蚕を行い、その生糸で稼いだお金で設備を近代化し、ついには絹は日本の主要産業と呼ばれるまでに成長しました。

昭和になり日本の養蚕、製糸業は世界シェアの約7割を占めるまでに順調に成長します。
しかし1930年頃アメリカを皮切りに世界中で起こった深刻な世界恐慌、1940年頃から始まる第二次世界大戦、時を同じくして低価格で大量生産が可能な化学繊維の誕生で生糸の需要は急激に落ちていきました。
終戦後の復興期1960年頃、養蚕業は少しずつ回復の兆しを見せていましたが、農業人口の減少・都市化・農地の減少・化学繊維の発達が進み、日本の養蚕・製糸業は衰退の一途を辿りました。
日本の製糸業の象徴でもあった富岡製糸場でも生産量が激減、ついに昭和62年3月、製糸場としての長い歴史に幕を閉じることとなりました。

現在の日本の養蚕農家は約500戸を下回り、絹生産量は最盛期の約1割程度になりました。
しかし近年、絹の価値も見直され世界での需要は再び急拡大しています。
絹の産地では昔からの生産大国である中国に加え、インド、ブラジル、ウズベキスタンといった国でも生産量が増えています。
日本では養蚕業は縮小していますが近年、繊維製品だけではなく化粧品・健康食品そして医療分野などさまざまな用途で絹の可能性が期待され開発・研究が進められています。
絹は紀元前より前の遥か昔より人々に大切に守り続けられ、愛されてきました。
そしてこれからも私たちにその魅力・価値・伝統を未来に広げていくものであると信じています。
